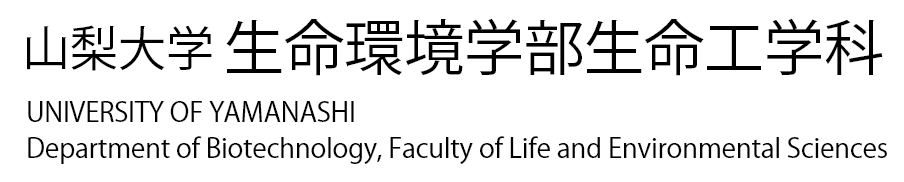3年生の生物工学実験I、あっという間に…
3年生の生物工学実験I、実施期間が例年より短かったため、あっという間に最終週を迎えました。前回の実験紹介の後、脂質、酵素、アミノ酸とタンパク質に関する生化学実験を行いました。いずれも生きた酵母から目的物質を抽出します。そして、どの実験も菌体破砕から始まりますが、どの物質に注目するかによって、その後の処理・操作方法を変えると「見たいものが見える、知りたい物質を追跡することが出来る」ようになります。これこそが生化学実験の醍醐味です。今回は最後に実施したアミノ酸とタンパク質の実験を紹介します。
1つ目の実験では、ペーパークロマトグラフィーという分析法を使って未知アミノ酸を同定します。タンパク質は20種類のアミノ酸からなりますが、アミノ酸はそれぞれ固有の化学的性質を持ちます。それぞれのタンパク質は遺伝子に記録されているアミノ酸配列通りに直鎖状に連結され、さらに固有の形に折れ畳まって初めて機能を発揮する分子となります。その際、アミノ酸の組成や配列が異なれば、異なる性質や機能を持ちます。そこで、各アミノ酸の化学的性質の違いを利用して未知アミノ酸の正体を暴きます。
標準タンパク質と未知試料を分析用のろ紙にスポットします。細いガラスキャピラリーを使って慎重にスポットします。慌ててスポットすると、試料がろ紙上で拡散し、ピンボケな仕上がりになってしまいます。
↑アミノ酸のスポットを慎重に行っています。
スポットが完了すれば、展開溶媒(主に有機溶媒)をろ紙に吸わせます。その吸い上げの流れにスポットされたアミノ酸も乗りますが、化学的性質の違いにより、移動のスピードが異なります。展開終了後、ニンヒドリンを使ってアミノ酸を発色し、移動度をもとにして、標準アミノ酸との比較によって未知物質を同定します。

↑ペーパークロマトグラフィーの展開(インスタントコーヒー瓶)は1時間ほどかかるので、待ち時間を有効利用してノートを書いています。

↑発色試薬(ニンヒドリン)は危険な試薬なので、教員が噴霧します。
↑未知物質の同定についてディスカッションをしています。正しく解明できたでしょうか?
2つ目の実験は、パン酵母からタンパク質を抽出し、その定量を行う実験です。より正確には、酵母菌体を破砕すると色んな物質が水溶性画分に抽出されていますが、タンパク質と特異的に反応する試薬(ビュレット試薬)を用いてタンパク質”だけ”を着色し、標準物質と比較することによって、酵母から抽出したタンパク質量を解析します。
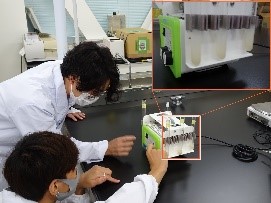
↑酵母をミキサーにセットして、破砕を行っています。

↑破砕後、水に溶ける成分だけを分離するため、遠心分離機にかけます。

↑遠心分離後、慎重に上澄み液を分取しています。

↑発色反応後、色の濃さを吸光度測定により数値化し、酵母から抽出したタンパク質量を計算します。
実験室での実習は終了しましたが、仕上げに、実験結果をレポートにまとめて提出します。レポートの内容に関して「100点の解答例をインターネットから探してくるのではなく、実験結果の整理と独自の調査に基づく自分だけの考察を盛り込んだオリジナル作品を100点にしよう!」をキーワードとしたレポート作成を提案しています。誰にも真似できないオリジナルな100点をお待ちしております!
実習は、次の生物工学実験IIに移ります。次の実習では、細胞培養工学と発生工学を学びます。引き続き、精力的に実験に取り組んで下さい。
本実習については、タンパク質構造生物学研究室 Web ページ(https://takujioyama1970.wordpress.com/)でも掲載していますので、興味があれば是非ご覧ください。